「子育て」にも「アドラー心理学」は、ヒントが満載です。
- 「上手く行かない…」
- 「後悔していることがある…」
- 「疲れてしまっている…」
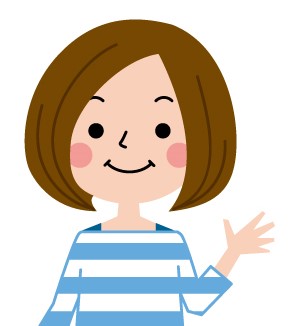
そんなあなたにとっては、この記事を読むと新しいアプローチ法が見つかって、これから先の子育てが楽になる可能性が有ります!
こちらのサイトでは、アドラー心理学の記事がコンスタントに読まれています。関心の高さを感じています。
以前に「子育てでのアドラー心理学」についての記事を書きました。
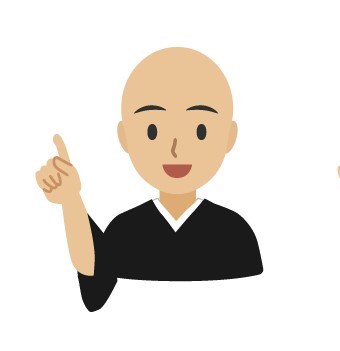
男性の私は長らくの間、「子育て」を嫁さんに任せきりでした。
2013年に仕事上の事で精神的に弱ってしまい、会社を辞めちゃいました…。
そんな時に出会ったのが「アドラー心理学」です。
アドラー心理学と出会って以降、「自分の価値観」が変わったのが実感できます。
そして、アドラー心理学を学んでいるお陰で、子供や嫁さんとの関わり方や関係性が変わり、アドラー心理学を学ぶ前の自分と比べると、家族との関係が「良くなった」と感じます。
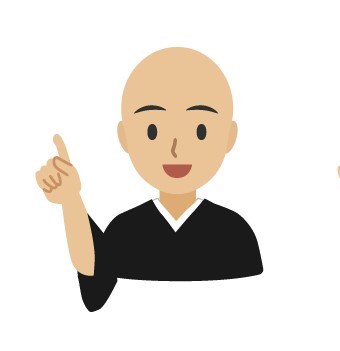
その経験を基に、お役に立てないかと思って、このように記事を書いています。
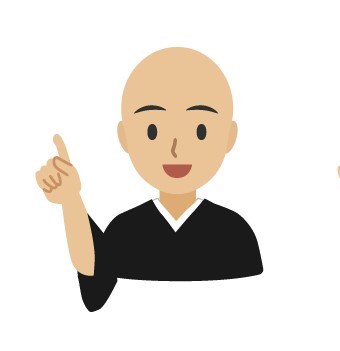
子育ての中で「上手く行かない…」「後悔してしまう…」「疲れた…」、そんな事を考えているあなたのお役に立てれば嬉しいです。
- 「上手く行かない時も皆あるんですよ」
- 「後悔するのは分かるけれど、もっと気楽に行きましょう!」
- 「疲れちゃうけれど、こんなアプローチも有るんですよ」
子育てにも「アドラー心理学」
アドラー心理学は、心理学と名前が付いていますが、人や自分を分析する心理学ではありません。
「自分が自分らしく生きるための実践法」がまとめられている「考え方・教え」なのです。
だから、アドラー心理学と言うよりも「アドラー思考法」と呼んだ方が分かりやすいのかもしれません。
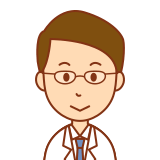
「自分との関わり方・他者との関わり方」について、「アドラーさんが考えた基本的な考え方」をまとめてくれています。
どうすれば「自分と他者との関係において、自分は幸福感を得られるのか?」をまとめてくれている、とも言い換えることが出来ます。
次の記事で「アドラー心理学」をシンプルに分かりやすくまとめています。➡心理学が楽に生きる役に立つ!今日から使えるアドラー心理学
子育てが「上手く行かない、後悔してしまう、疲れた…」時に参考になる本
「子育て」でアドラー心理箔を上手く活用している良い本を見つけちゃいました!
アドラー心理学を学んでいる私は、アドラー心理学について書かれた本には興味を持ってしまいます。
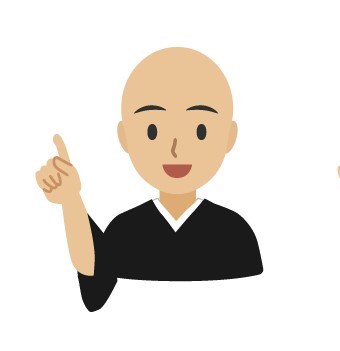
「アドラー心理学の子育ての本」となると、どうしても「親と子供の関わり方」についてばかり書かれがち…。
「お母さんの立場に寄り添い、お母さんの不安などにも踏み込んだ内容」が不足しているように感じていました。
ところが、この本はその面においても「素晴らしい」と感じました。
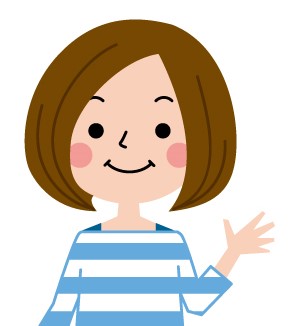
その本の名前は【ほめるより子どもが伸びる「勇気づけの子育て」:原田綾子さん著:マイナビ文庫】。
*この記事は上記の著書を参考に書き進めています。(参考・引用・転載先「勇気づけの子育て」原田綾子さん著)
「勇気づけの子育て」本について
著者は、元小学校教員で自分の子育ても経験している1974年生まれのお母さん、原田綾子さん。
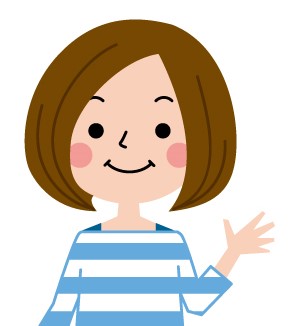
原田さんは、「勇気づけの親子教育専門家」として講演や執筆などの活動を行なっています。
そうなんです、この本は、アドラー心理学を基に、分かりやすく「勇気づけ」を教えてくれています。
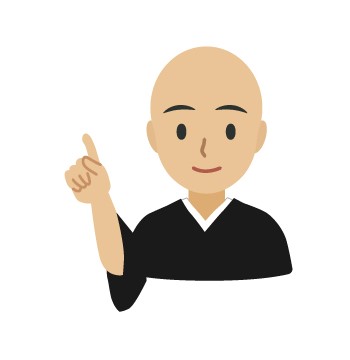
だから、お母さんも勇気づけられます!
そして、「子供を勇気づける」とは何なのか? を分かりやすく説明してくれています。
まずは、「お母さんへの勇気づけ」が必要
お母さんに対する「勇気づけ」については、冒頭の「はじめに」の5ページ中ほどから書かれています。
そして、第4章「お母さんと子供の心はつながっている」・最終章の第5章「お母さんの心を勇気のエネルギーで満たそう」は、すべて「お母さんの心に寄り添った勇気づけ」の内容です。

「親の心が不安定だったり、どこか無理をしていると、その歪みが子供に映し出されてしまう」、
そんな傾向が強いようです。
お母さんの心に寄り添った「勇気づけ」
「子どもを勇気づける」ことは、子どもが自信を付けたり、やる気を引き出すうえでとても大切です。
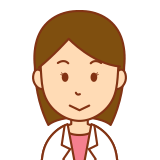
と言うことは、
「お母さんを勇気づけることは、お母さんが自信を付けたり、お母さんのやる気を引き出すにも重要です!
そして、親子は繋がっているので、お母さんがお子さんを勇気づけていても、親が下記の状態だと、実は子育てにも影響します。
- 心が不安定
- 感情にフタをしている
- 無理をしている
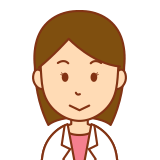
つまり、子育てをする上で、日ごろからお母さんの心を整える必要があります。
「お母さんの心を整える」には?
「自分の今の心の状態を感じることが良い」と本には書かれています。
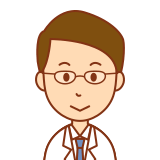
いま私は、
- どんなことを思っている?
- 何を感じている?
- 本当はどうしたいの?
と自分に問いかけてみてください。
そして、「その感情にフタをしない、また、無理をしない」、そんなコツを掴んでください。
それが、「心の安定=心が整う状態」に繋がります。
心を整えるアプローチ
本には、7つのアプローチが紹介されていました。
①「自分の感情を第3者的に感じてみる」
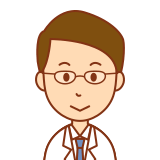
自分の親友と向き合っていると思って、自分の事に向き合ってみてください。
自分が自分にとって、「世界で一番の味方」になってください。
それが、「自分を勇気づける」ことでもあります。
- 「よく頑張っているね」
- 「出来ないことは、誰にだってある」
- 「後悔することは誰にだってある」
- 「完璧な人なんていない」
- 「誰でも最初から、上手には出来ない」
- 「いつもがんばっている姿、素敵だと思っているよ」
こんな言葉を自分に掛けてあげてください。
②「引き算で考えない」
「自分の考えるお母さん像」や「他のお母さん」と比べて、「自分は出来ていない」「自分はこれが足りない」と引き算をしないでください。
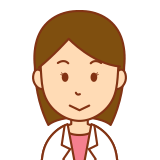
「こうなりたい」「こうしたい」と思うことは大切なことですが、「直ぐには誰も上手く出来ません!」「すぐにはコツは掴めません!」。
「こんな時も有るさ」「少しづつでも良くなっていこう」の気持ちで、大らかに自分を見つめてください。
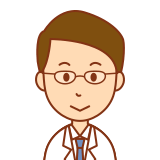
結局、「お子さんに対しても同じ」なのです。
お子さんが出来ないことがあっても、「こんな時も有るさ」「少しづつでも良くなっていこう」という大らかな心をお子さんに向けてください。
③「自分を勇気づける」
自分で自分を勇気づけることが出来たら、自分の心を元気にすることがしやすくなります。
そして、子どもにも勇気づけがスムーズに出来るようになります。
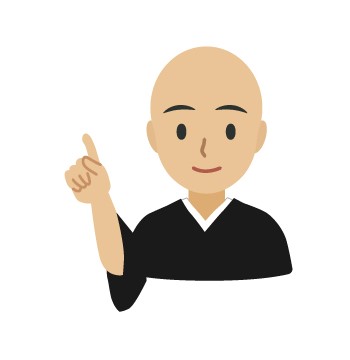
- どんな自分もOKと肯定する。
- 短所も含めて自分にOKを出す。
④失敗を成功の糧(かて)とする。
「あきらめない限り、失敗なんてない」という金言があります。
ほんと、そうですね!
⑤ネガティブな感情も大切にする。
落ち込むことや自信を無くすこと、悲しいこと…。
人生はいろんなことが起こります。でも、その感情にフタをせずに、落ち込むときは落ち込んで、マイペースで復活する。そんな心の整理をしてください。
⑥悩みをチャンスに変える。
悩みは自己成長のチャンスです。
⑦自分を信じる。
生まれてから死ぬまで、自分といつも一緒にいるのは自分だけです。
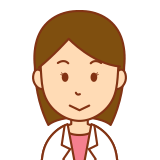
どんな時も自分の味方で自分を信じたいモノです。
お母さんの心が整う実践法
実際の実践法の例を紹介してくれています。
がんばりすぎなくて良い

がんばりすぎなくて良いんです。
あなたはいつも、自分が出来る範囲で「がんばっている」のです。力を抜くときも当然あります!
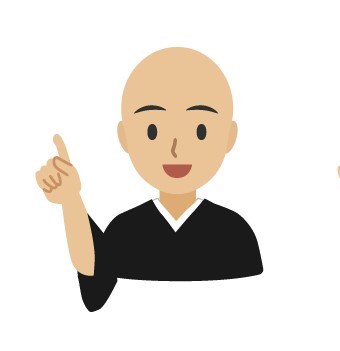
「もっとがんばらなきゃ」って思ってしまう人は、この記事の最後に紹介する「ひろさちやさん著の”そのまんま そのまんま」という本をおススメします。肩の力が抜けて、とっても心が軽くなります。
心が元気になることをしよう!!
実践法として、次の事が「勇気づけの本」には書かれています。
自分の時間を作る
たとえ、1日に5分でも10分でも、「自分の時間」を作ることは出来ませんか?
出来るならば、たまには、親御さんか旦那さんか誰かに甘えて、少し長めの自分の時間が取れれば良いですね。
わくわくノートを作る
自分がワクワクする事をノートに書いてみたり、写真を貼ってみたり。たまには、お子さんにイラストや言葉を書いて貰っても良いと思います。
部屋に花を飾る
自分の空間に「自分の好きなモノ」を置いてみましょう。
その他
- 素敵なカフェでお茶をする
- 部屋を整える
- 嬉しい記憶を思い出す
- 子どもが赤ちゃんだった頃のアルバムや写真を見る
- 大好きなことに時間を使う
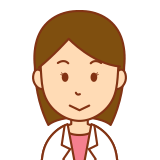
こういったことで、心にエネルギーを注いでください。
「自分が考えるお母さん像」とは?
この記事を読まれているあなたは、「自分が考えるお母さん像」と自分を比較する場合が多いのではないでしょうか?
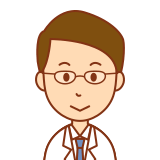
たいていは、「自分が子供の頃に、自分のお母さんにして欲しかったこと・して貰えなかったこと」を自分の理想にしがちです。
そんな場合は、自分が作る理想やルールに囚われて、理想と現実のギャップに悩みがちです。
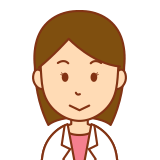
ところが、それにとらわれ過ぎて、お母さんの心が不安定になったり、自信を無くしたり、疲れてしまうと、子育てに影響します。

子どもさんの一生を左右するとしたら、
おおらかになれずに「いつもイライラ、いつも怒ってばかり…」、そんな状態ではないでしょうか?
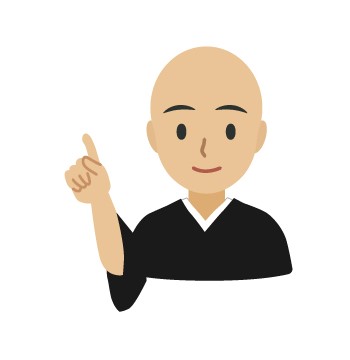
この記事を読んでいるあなたは、そんな「今の状況をなんとかしたい」と思われています。
だから、
「自分を認める・自分を許す・自分を受け入れる」おおらかさを、もっともっと身に付けてください。
そうすれば、状況は良くなるので心配ないと私は思います!!
ですので、「自分にも子育てにも、おおらかに」関わることをおススメします。
「立派なお母さん」ではなく「幸せなお母さん」になろう
子育てに悩みがち・ストレスを抱えやすい人に多いのが、「べき・ねば」の考え方の強い人です。
物事を「良い・悪い」「白・黒」とキチンと決めたい傾向の人も、同じような傾向性が有ると心理学では言われています。
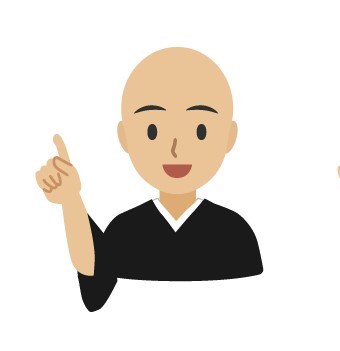
この本で、私がいちばん好きになった個所を、次に紹介します。(P248~249)
力まずに、ありのままの自分で、今自分にできることを全力でやっていくこと。
そして、うまくできるとか、できないとかではなくて、日々子どもたちと全力で楽しむこと。泣いたり、笑ったり、感動したりすること。
自分自身についても、できないことに焦点を当てるのではなく、できていることに目を向け、ちょっとがんばればできそうな「1.1倍の目標」を持ち、今を全力で生きること。
どんな自分もOKと受け入れ、日々の小さな成長も認めて自分を勇気づけられるようになってからは、楽しく、わくわくと取り組めるようになっていきました。
きっと、自分の中で「不完全な自分を受け入れる勇気」が持てたのだと思います。過去の後悔や、未来の不安を考えるのではなく、今できることに集中する。「勇気づけの子育て」原田綾子さん著:マイナビ文庫
「勇気づけ」
「ほめる」ことも大切ですが、「ほめるよりも、勇気づけが良い」という考え方がアドラー心理学には有ります。
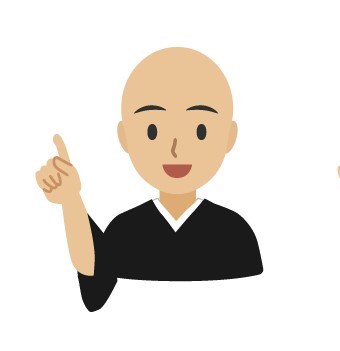
「勇気づけ」という言葉をアドラー心理学では使います。
「勇気」とは?
この本では、「勇気」とは、「困難を克服する力」と書かれています。
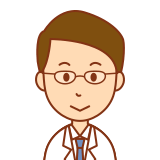
この「勇気」は人間が本来に持っている力です。
➡「子育てでの勇気づけ」とは「親が子の力を引き出していく」ということです。
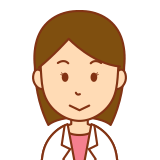
「困難を克服する」には、「自分は出来る」という「自信」が必要です。
➡「勇気づけ」とは「自信を育む」と言い換えられます。
「勇気づけ」とは?
「自信を育てる」ことです。
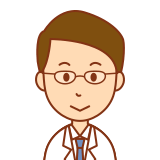
「自分の力で」出来るようになることです。
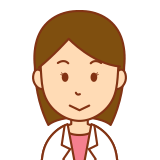
「自信付け」を助ける行為が「勇気づけ」です。
「勇気づけ」の基本
ポイントは3つです。
- 共感
- こちらのプラスの気持ちを伝える
- 「注目しているよ」というメッセージも大事
最後に
ほめないよりは「ほめたほうが良い」のですが、ほめるよりも「勇気づけ」を中心に取り入れてみることをおススメしました。
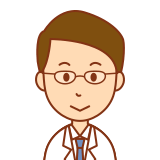
親も子も「勇気づけ」は、自分の自信に繋がります。
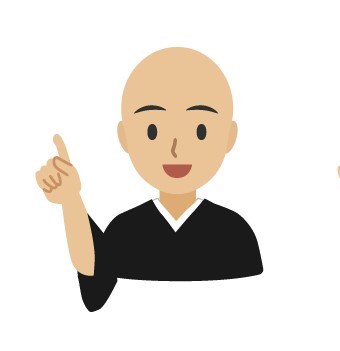
自分に対しておおらかに、「自分のお子さんと接するように自分と接してみる」ことがポイントなのだと、この本を読んで感じました。
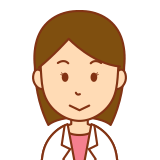
おおらかに、自分やお子さんの「勇気づけ」チャレンジしてみてください。
お子さんの「勇気づけ」は、お子さんの「自信・自立心」を育てることに繋がります。
子どもが困らないように、と親が手を出してしまったり、先回りをして対処してしまうと、「問題を乗り越える大切な機会を逃す」ことになります。
子育ての目標は、子どもを自立させることです。子どもが自立することをサポートするのが親の役目です。
大事なのは、親が先に答えを与えないということです。子どもが自分の力で答えを出せるように導くことが大切です。(P94)
アドラー心理学は、「対自分」そして「対人関係」にとっては、とても有益ですので、興味のある方は、学んでみてください。

アドラー心理学では「課題の分離」と言う言葉が有ります。
子育てでの課題の分離は、この記事で書いています。👉子育てに活かせるアドラー心理学の「課題の分離」とは?
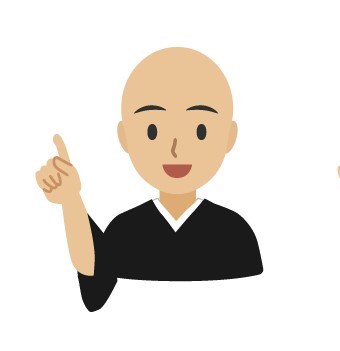
最後に、この記事を読んでくださったお母さん・お父さんにお礼を申し上げます。
この記事を最後まで読んでくださることは、私の「勇気づけ」になりました。
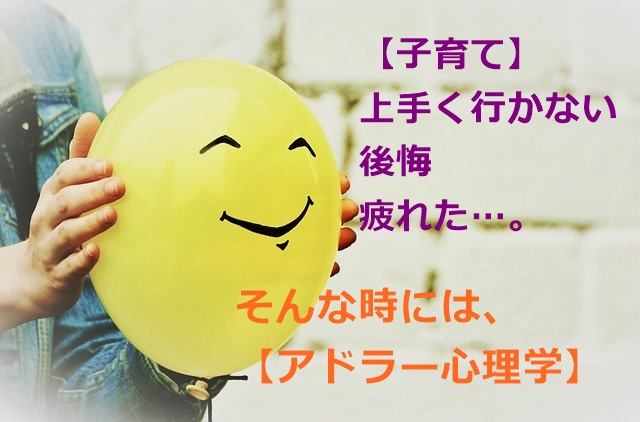


コメント
Twitterから来ました。
子育て、アドラー、法事等の情報がとてもスッキリとまとめられていて感動しました。とても読みやすく、思いやりが感じられます。参考にさせていただきます。特にアドラーをもう一度復習します。ありがとうございました